平安の貴族にとっての装束(しょうぞく)は、身分や財力、センスを示す重要な“見た目の名刺”でした。
一方で当時の貴族社会には厳格な服装ルールがあり、場や身分にかなう衣を着る必要がありました。
2024年(令和6年)放送のNHK大河ドラマ『光る君へ』でも、物語の進行とともに登場人物の装束に大きな注目が集まったのは記憶に新しいのではないでしょうか。
というわけで本記事では、平安の男女が守ったドレスコードと装いをわかりやすく、かつある程度詳しく紹介します!
平安時代の男性貴族の服装
男性貴族の本務は天皇の政務を補佐する官人で、勤務先である朝廷(=政府)はとても神聖な場所であるとされていました。
そのため参内の際は改まった正装を用います。
現在で例えると、テレビに天皇皇后両陛下が出ているとき、隣にアロハシャツの人が立っていたらおかしいですよね。
なので、きっちりした服装をしていた…というわけです。
一方、私的な場では洒落た普段着を楽しみ、TPOに応じて着替え分けていました。
ここでは男性貴族の正装・準正装・日常着を見ていきます。
正装・束帯で朝廷に出仕
束帯(そくたい)は、男性貴族が朝廷へ出仕する際の礼装です。
基本の組み合わせは、着物+袴に、上から袍(ほう)を重ね、石帯(せきたい)という帯を締めます。
特徴的なのは、袍の下に着る下襲(したがさね)の背面が長く引きずる点。
引きずる部分は裾(きょ)と呼ばれ、位が高いほど長くなりました。
さらに袍の色は位階(いかい:身分序列。一位が最上位)で決まっていました。
『光る君へ』では、ヒロインまひろの父で下級貴族の藤原為時(ふじわらのためとき)は緑、上級貴族の藤原兼家(ふじわらのかねいえ)は黒の袍を着用。
これは平安中期の規定――四位以上は黒、五位は赤、六・七位は緑――の再現です。
武官束帯・朝廷警護役の制服
武官束帯(ぶかんそくたい)は、天皇や皇族の護衛を担った官人の装い。
動きやすいよう袍の脇は縫い留めず、冠の後ろで垂れる纓(えい)は巻き留めます。こめかみ付近には馬毛で作る飾り・緌(おいかけ)を付けました。
『光る君へ』では、成人後に初登場する藤原道長(ふじわらのみちなが)が赤い武官束帯を着ています。
道長が14歳で初任の位階(五位=赤の袍)を授かり、官職が武官の右兵衛督(うひょうえのかみ)だったという史実に基づく演出です。
準正装・衣冠は夜勤用の略式
衣冠(いかん)は、宿直時に着る束帯より簡略な服装。
石帯と長く引きずる裾を省き、ゆったりした袴=指貫(さしぬき)をはきます。
目的から宿直装束(とのいそうぞく)とも呼ばれ、対して束帯は昼の装束(ひのそうぞく)とされました。
普段着・直衣は自由な色柄
直衣(のうし)は男性貴族の私服にあたり、見た目は衣冠に近いものの、公服ではないため位階や官職に縛られず色柄を自由に選べました。
『光る君へ』では、権勢を誇る藤原兼家が富と権力を示すかのように鮮やかな直衣を着用。
男性貴族はこの直衣姿で私的な歌会や花見・月見の宴に出席しました。
御簾(みす)の内に座す女性とは気軽に言葉を交わせないため、男性は装いで視覚的にアピールしたのです。
日常着・狩衣は軽快に着こなす
狩衣(かりぎぬ)は本来狩猟用の服で、動きやすいよう両脇を縫い合わせない造り。
着心地が楽なため、男性貴族は日常の私服としても好んで着ました。『光る君へ』では、まひろの親戚・藤原宣孝(ふじわらののぶたか)が度々この姿で訪ねてきます。
陽気で世渡り上手、女性にもまめで妾(しょう)が複数いると描かれる彼の享楽的な人物像に、色鮮やかな狩衣がよく似合います。
平成時代の女性貴族の服装
女性の正装は、のちに「十二単(じゅうにひとえ)」と呼ばれる装いです。
学生時代に聞いてこれだけは覚えている、という方も多いでしょう。
宮中に仕える女性の正礼装で、『光る君へ』では藤原詮子(ふじわらのせんし/あきこ)が円融天皇(えんゆうてんのう)の后として入内する場面で着ていました。
何枚も重ねるため重さは約10kg。
ただし常にフル装備ではなく、やや軽い略式も存在しました。ここからは女性貴族の正装・準正装・外出着を紹介します。
正装・十二単は“12枚”とは限らない
女性の正装を「十二単」と呼ぶのは後世の通称で、当時は裳唐衣(もからぎぬ)や五衣唐衣裳(いつつぎぬからぎぬも)と称しました。名称の由来は、表着の唐衣の下に五衣(ごろも)と呼ばれる5枚の衣を重ね、その上で巻きスカート状の裳を付ける構成にあります。
実際の重ねは12枚より少ないことが多いものの、多層で成る点が特徴。上に着る順に主な構成を見ていきましょう。
唐衣
最上層に羽織る最も華やかな衣。丈は短く腰あたりまで、袖も短めで、下層の色合わせ(配色)を見せる設計です。
表衣
表衣(うわぎ/うえのきぬ)は唐衣の下に着用。下に重ねる色を覗かせるため、やや小ぶりに仕立てます。
打衣
打衣(うちぎぬ)は表衣のさらに下。生地を叩いて艶を出す加工に由来する名称です。
袿/五衣
袿(うちき)は打衣の下に数枚重ねる衣。古くは10枚以上でしたが、平安期には5枚が定着し「五衣」と呼ばれました。この5色の組み合わせで季節感を表す配色を「襲色目(かさねのいろめ)」といいます。上着類を小さめに仕立てるのは、袖口・襟元・裾から襲色目を美しく覗かせるためで、女性のセンスの見せ所でした。
単衣
単衣(ひとえ)は裏地のない肌着にあたる着物です。
裳
腰の後ろだけを覆い、長く引きずる巻きスカート状の装具。白・赤・青のほか、上部を淡色、裾へ向かって濃く染めた「裾濃(すそご)」もあります。
長袴
長袴(ながばかま)は筒状のロングスカートのようなもので、裾を引きずるほど長いのが特徴。歩くときは裾を踏みながら前進しました。色は年齢で使い分けたとされ、未婚の若い女性は紫、既婚または年長の女性は濃い赤を用いたという説があります。
準正装・小袿/袿袴は高貴な女性の普段着
小袿(こうちき)または袿袴姿(うちきはかますがた)は、正装の十二単から唐衣と裳を外した装い。
『光る君へ』では、入内後の藤原詮子の平時の姿や、まひろと源倫子(みなもとのともこ/りんし)が交流する場面で見られ、女性貴族のプライベートな装いだったことがわかります。
なお、まひろの表着(うわぎ)は艶控えめで柄も落ち着く一方、皇后の詮子や上流貴族の倫子は、地紋が浮かぶ艶やかな生地に金糸・色糸の文様を織り出す豪華な表着で、布地の格からも身分差が表現されています。
外出着・壺装束は顔を隠すのが嗜み
壺装束(つぼしょうぞく)は、身分ある女性の外出用スタイル。
歩きやすい短めの切袴(きりばかま)をはき、市女笠(いちめがさ)には枲垂衣(むしのたれぎぬ)という覆いが付いて顔を隠せます。
もっとも上流の女性が徒歩で出る機会は限られ、移動は牛車(ぎっしゃ/ぎゅうしゃ)が一般的でした。
『光る君へ』のまひろは町に出て人々の暮らしに触れる場面が多く、序盤では市女笠を従者の乙丸(おとまる)に持たせたまま被らないおてんばな姿も。
縁談が持ち込まれる年頃になると壺装束での描写が増え、大人の女性へと移ろう様子が装いからも伝わります。
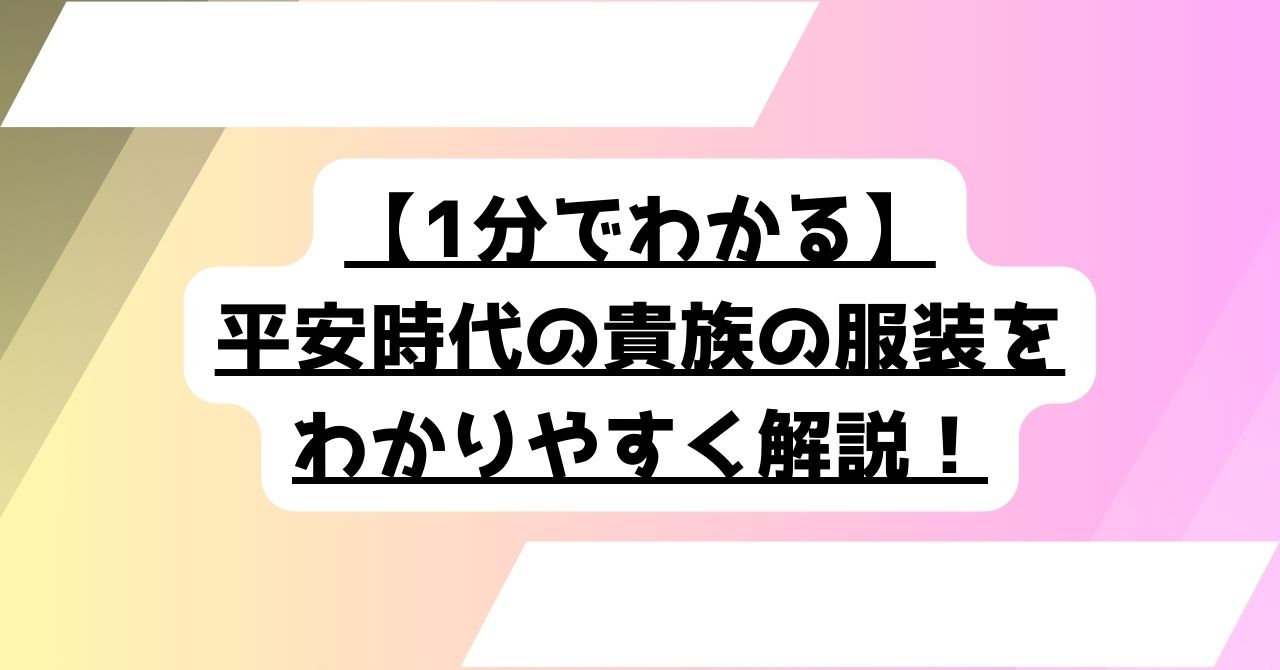
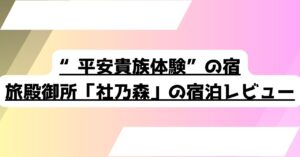
コメント